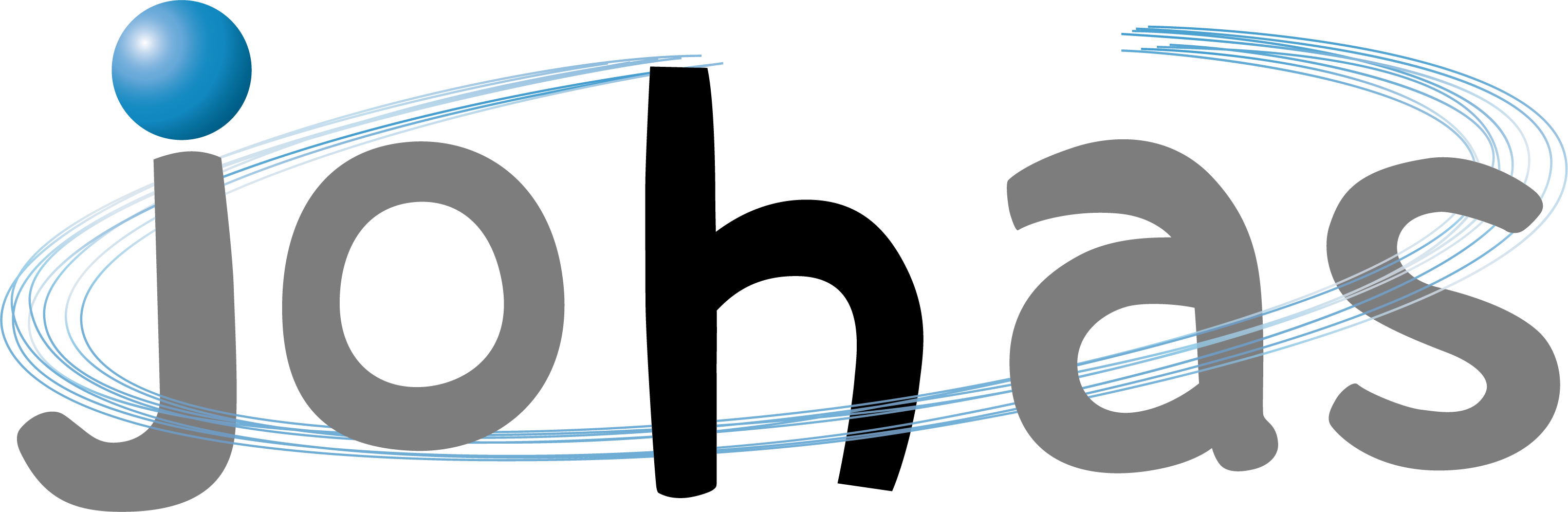身体的拘束最小化のための指針
1. 身体的拘束の定義
身体的拘束とは「本人の行動の自由を制限すること」である(厚生労働省老健局. 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き, 2025)。患者の安全保持と治療、看護上の必要性による運動制限の目的で、体幹ベルトや上下肢への抑制帯、ミトンなどの物理的手段を用いて患者の自由な行動を制限する方法を指す。表 1 身体拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為(例)
| 1 | 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る |
| 2 | 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る |
| 3 | 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む |
| 4 | 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る |
| 5 | 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける |
| 6 | 椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける |
| 7 | 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する |
| 8 | 脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる |
| 9 | 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等でしばる |
| 10 | 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる |
| 11 | 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する |
(厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」. 身体拘束ゼロへの手引き, 2001)
移動時などの安全確保のため短時間固定ベルトなどを使用する場合、その間、常に職員が介助等のため当該患者の側に付き添っている場合に限り身体的拘束には該当しない。2. 私達の身体的拘束に対する考え方
平成12年度介護保険制度の施行時から、介護保険施設などにおいて、高齢者をベッドや車いすに縛り付けるなどの身体の自由を奪う身体的拘束は、介護保険施設の運営基準において、サービスの提供に当たっては、入所者の「生命および身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き」行ってはいけないものとされ、原則として禁止されている(身体拘束廃止とその取り組み:1999年3月31日 厚生省令第9号 身体拘束廃止に関する省令)。 また、身体的拘束は、憲法第31条「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」という規定に反するものである。 しかし、急性期医療の中で患者の病態等によっては、安全確保や治療効果を十分に発揮させるために、やむを得ず身体的拘束しなければならない状況もある。身体的拘束を実施する上では、明確な根拠と正当性がなければならないが、たとえ明確な根拠と正当性が認められる場合でも、できる限り身体的拘束をせずに済む方法を考えること、身体的拘束が実施された場合においても早期に解除できるよう努めるのが私達医療従事者の役割の一つである。 私達は「身体的拘束をしないための具体的なケア」を追求しつつ、不要な身体的拘束を少なくするために、十分なアセスメントと患者、そのご家族の方への十分な説明を行い、医師の指示をもって根拠に基づいた安全で効果的で最小限の身体的拘束を実施する。3. 身体的拘束廃止に向けて(5つの方針)
- トップが決意し、施設や病院が一丸となって取り組む
- みんなで議論し、共通の意識をもつ
- まず、身体抑制を必要としない状態の実現をめざす
- 事故の起きない環境を整備し、柔軟な応援体制を確保する
- 常に代替的な方法を考え、身体的拘束するケースは極めて限定的に
4. 身体的拘束の原則:緊急やむを得ない場合
3つの要件「切迫性」「非代替性」「一時性」を全て満たされている必要がある。(1) 「切迫性」:抑制を行わなかった場合は生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い
A 病状により自傷、他傷の恐れがある。
B 意識障害、興奮性があり、身辺の危険を自身で予測できない・回避できない。
(2) 「非代替性」:身体的拘束・行動制限を行う以外の方法がない
C 環境調整や気分転換、コミュニケーションの工夫など、さまざまな非拘束的アプローチを試みても効果がなく、転倒やベッドや車椅子からの転落の可能性がある。
代替の例:睡眠リズムを整える、低床ベッドにする、床にマットを敷く
(3) 「一時性」:身体的拘束、その他の行動制限が一時的である
D 興奮状態により自傷他害の恐れがある場合の一時的な拘束
(状態が落ち着いたら速やかに解除)
E 医療処置のために一時的に拘束が必要な場合
(処置が終わり次第速やかに解除)
5. 鎮静を目的とした薬物の適正対応
一過性不眠に基本的に睡眠薬は不要である。適切な評価を行い、不眠に対する薬物療法が必要と判断された際には、せん妄を惹起する可能性や睡眠薬・鎮静薬による耐性や離脱症状、乱用のリスクを考慮した上で検討を行う。6. 身体的拘束最小化のための体制
院内に身体的拘束最小化対策に係る身体的拘束最小化チームを設置する。1)身体的拘束最小化チームの構成
チームは医師、看護師、メディカルソーシャルワーカー、事務員など多職種で構成する。2)チームの役割
- 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する。
- 身体的拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する。
- 定期的に本指針・マニュアルを見直し、職員へ周知して活用する。
- 身体的拘束最小化のための職員研修を開催し、記録をする。
7. 身体的拘束最小化のための職員教育、研修
医療・ケアに携わる職員に対して、身体的拘束最小化のための研修を実施する。- 定期的な教育研修(年1回)実施
- その他、必要な教育・研修の実施および実施内容の記録